こんな人におすすめ
- 半年の職歴って書類に書けばいい?
- 初めての職務経歴書は何に注意する?
- 第二新卒の職務経歴書とエントリーシートは違う?
※クリックすると、読みたいところにジャンプするよ
「はじめての転職で短い職歴しかなく不安」そう思ったことはありませんか?
転職では新卒採用と違って自分より経験がある人がエントリーすることも考えると、半年未満の職歴でアピールできるか不安になりますよね。
短い経験がマイナスになって転職がうまくいかないことを考えると寝られない日もあるのではないでしょうか。
ですが、半年未満の職歴であってもポイントを知れば、内定獲得できる職務経歴書をつくることは十分可能なのです。
ここでは大手人材会社でコーディネータとして紹介実績1000名以上・キャリア相談実績100名以上のキャリアコンサルタントなべけんが、半年の経験でも選考通過できる3つのポイントを紹介いたします。
第二新卒の職務経歴書で意識すること
転職をするときに第二新卒の方は、期間が短いということを自分で勝手にマイナスと捉えてしまう方が多いです。
しかし自分では気づいていなくても、社会から見たらプラスのことも多くあります。
第二新卒は周囲との比較ではない
第二新卒になると年が異なる人のエントリーしており、周囲と比べてしまいますよね。ですが、第二新卒の転職では必ずしも比較が行われているわけではありません。
「仕事を任せられるかどうか」で判断されるので、極端に考えると1人も採用されないこともあるのです。
そのため、自分ができることをアピールすることが重要なのです。
半年の職務経歴でも3つ意識すればOK
では、自分ができることは何を意識すれば良いのでしょうか。3つのポイントを意識することで、社会から求められていることをアピールできます。
- ビジネスマナー研修について書く
- 仕事内容をステップごとに書く
- ハードルを上げないで書く
そのポイントを抑えた職務経歴書の作成ができるよう確認していきましょう。
ポイント①:ビジネスマナー研修について書く
多くの新入社員は集合研修から始まりますが、研修を受けていることが転職で強みになることをご存知でしょうか。
また、ほとんどの方が受講している同じような研修も職務経歴書への書き方によって、周囲と差をつけることもできます。研修をアピールするときは、この2つをアピールすることで半年未満の職歴でもアピールできます。
- 研修内容
- 参加姿勢
研修内容をアピール
第二新卒は新卒採用とは異なり、即戦力人材として採用されます。そのため、ビジネスマナーなど社会人としての基本的な心構えがあることが前提で採用されることが多いです。
ビジネスマナー研修を受けただけでも、研修の手間を省けるためプラスの印象を与えることができますね。
研修内容の具体例
このように具体的に書くことで、どのような知識があるのか応募書類を通じて伝えられます。
- 法務研修(労働三法・労働者派遣法・労働契約法)
- ビジネスマナー研修(名刺交換・受注対応・クレーム対応)
- OJT研修(人材派遣新規営業・既存顧客営業)
- チーム制ロールプレイ大会1位/9チーム
研修内容は企業によって異なるため、研修期間を細かく記載するだけでアピールに大きくつながりますね。
研修を受けた第二新卒はやはり人気
わたしがお仕事紹介をしているときも、クライアントの必須条件に「ビジネスマナー研修を受けていること」が入ることが多々あります。
また条件になくても、研修を受けている求職者であればクライアントへのアピールを行っています。
参加姿勢をアピール
また、研修内容のアウトプットができていると、学びに対する積極的な姿勢をアピールできます。
第二新卒のように経験が浅い方は、ポテンシャル採用(ビジネス経験でなく人柄など重視)のため、物事へ取り組むスタンスは重視されています。
スキルとスタンスの違いとは
スキルとは経験を積んでできるようになったことで、スタンスとは物事に取り組む姿勢です。
そしてスタンスがポジティブな場合は、努力次第でどのようなスキルも身につけることができるため、重視している企業の多いです。
研修を「受ける」は△
研修を「受ける」という言葉を使うと、受け身な印象になってしまいます。そのため研修を通じて「どのように成長できたか」を、このようなことを意識してアウトプットしましょう。
- どのように考えていたか
- 何を学ぼうとしたか
- 何が得られて何が得られなかったか
このような研修の参加姿勢を意識するだけで、学びを深めることもできますね。
ポイント②:仕事内容をステップごとに書く
仕事は様々な要素で成り立っていますが、仕事を分解して考えることがとても重要になります。
これができていないと、下記のような業務内容になってしまいます。
- 受発注業務
- 伝票処理
- 経費精算
- 電話応対
この例では、「何を行ってきたのか」は分かりますが、「どれくらいの能力がある」のかはわかりません。では、どのように書けば良いのでしょうか。
定量的に書く
最も重要なことは、数字を使えるところは数字で書くことです。
また対応のプロセスも詳細に書くことで、面接官が抱くイメージが大きく変わりますね。
- 営業アシスタント(営業30名担当/2名体制)
- 資料作成(請求書類・見積書類・社外提案書類/Excel:1から作成)
- 受発注業務(電子部品:約100種類/使用システム:SAP)
このように定量化や方法を記載するだけでも、「100種類の部品を覚えられること」や「営業とコミュニケーションをとって仕事ができること」が伝わりますね。
プロセスごとに書く
さらに詳細を書くために、仕事をプロセスごとに箇条書きをしていきます。
これをすることで、経験したことの漏れを防ぐこともできますね。
たとえば、受発注業務の流れを見てみるとこのようになります。
- 納期調整(関連会社3社/20件/日)
- 問い合わせ対応(社内・社外/30件/日)
- 在庫管理(関連会社3社)
このように一連の流れで対応していた業務の漏れを防ぐことにつながります。
ポイント③:ハードルを上げないで書く
選考漏れにならないためにも、自分でハードルを上げずむしろハードを下げて書くという意識がとても重要になります。
「誰がやっても一緒」と考えてしまうと、下記のような業務内容になってしまいます。
- データ入力
- 書類作成
- 電話応対
- メール応対
このような書き方では、他の候補者と同じになりやすく書類選考で埋もれてしまいます。
では、どのようなポイントを意識すれば他の人と異なる経験をアピールできるのでしょうか。
人によって仕事の仕方は違う
誰が担当しても同じに感じる「データ入力」でも人によって仕事で意識していることは違いますよね。
たとえば、正確さやスピード、手順、意識していることなど。
つまり「なぜそのやり方で仕事をするか」を説明すると、自分しかできないデータ入力として説明することができます。
これを意識して書くと同じ業務内容でも下記のように変わります。
- データ入力(売上データ200件/日|Excel使用)
- 資料作成(クライアント提案資料・営業成績|PowerPoint使用)
- 電話応対(社内外20件/日)
- メール応対(社内外20件/日|Outlook使用)
また、自分では誰でもできると考えているデータ入力についても社会からの評価が同じとは限りません。
社会人経験が浅い第二新卒だからこそ自分ができることを最大化し説明できるようにしましょう。
まとめ:自分が経験したことをリアルに書く
自身が経験してきた仕事を棚卸しすることで、自分ができることもより明確になり自身に繋がったのではないでしょうか。
当たり前の基準を下げるだけで自身の市場価値を再認識し、短い期間でも得られたことを整理しました。
これにより自身ができることと目標へのギャップも明確にし、次へのステップアップに繋げていきましょう。
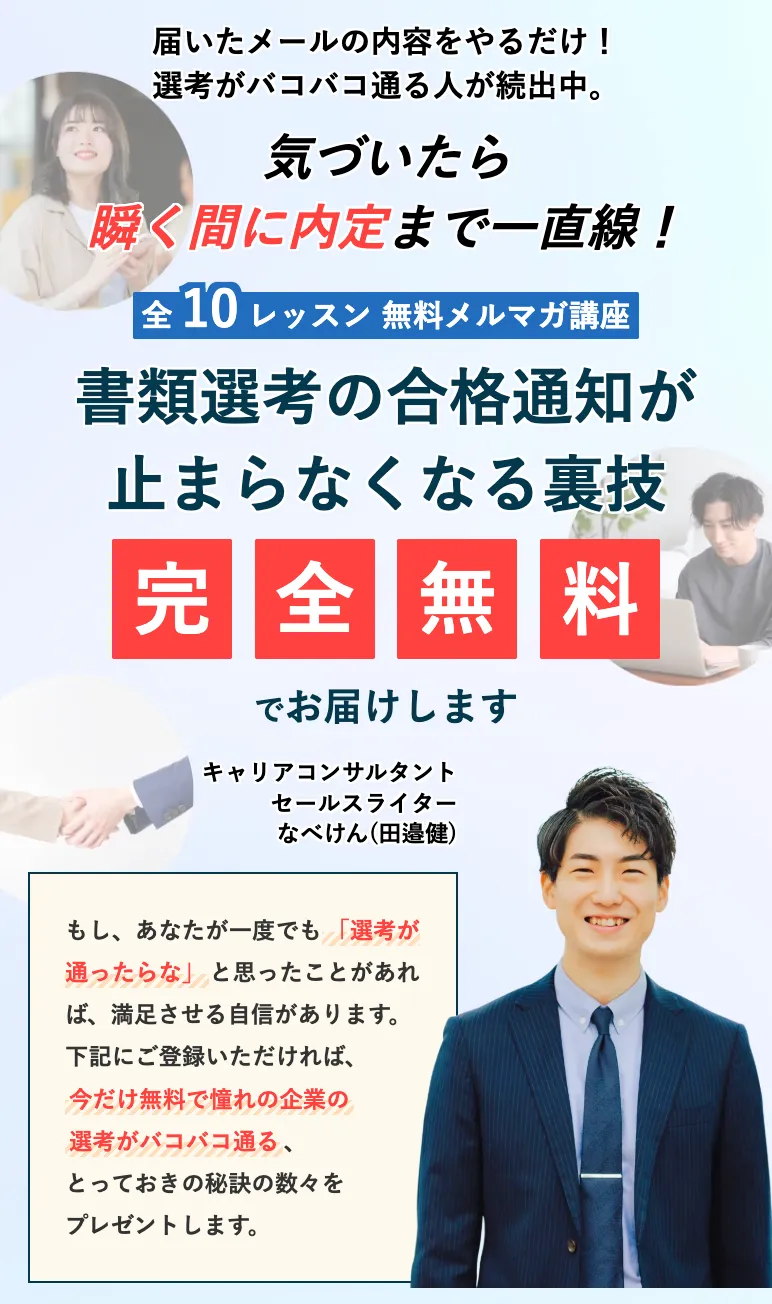

質問や感想をコメント