こんな人におすすめ
- 働いた期間が短くて転職が不安…
- 職歴が1年未満でどう経歴書に書けばいいか知りたい
- 職務経歴書に何をどう書けばいいか分からない
※クリックすると、読みたいところにジャンプするよ
「一年未満だから職務経歴書に書くことがない」このように悩んだことはありませんか?
一年未満だとアピールできる実績もなく書くべきかどうか悩む人も多いですよね。はじめての転職だと、短い職歴で内定獲得ができるのか不安になることも多いと思います。
ですが、一年未満の職歴も必ず職務経歴書に書くべきで、ポイントを押さえれば選考通過は必ずできます。
ここでは大手人材会社でコーディネータとして紹介実績1000名以上、キャリア相談実績100名以上のキャリアコンサルタントなべけんが、誰でも職務経歴書が書けるようになる3つのポイントをご紹介いたします。
一年未満の職歴で経歴書作成する3つのポイント
一年未満の職歴をマイナスに感じている人も多いですが、まずその考え方を変える必要があります。
第二新卒で職務経歴書を書くときには、この3つのことを意識しましょう。
- 他の第二新卒と比較しない
- 一番伝えたい経験を伝える
- 採用担当が気になることに答える
ポイント①ほかの転職希望者と比較しない
応募書類に書くことがないと悩んでいる方の多くは、”誰でもできる”や”簡単なことしかできない”と悩んでいらっしゃるのではないでしょうか。
このように他人と比較してしまいがちですが、他人との比較は間違いです。
就職活動で企業側が知りたいことは、誰かと比較して何ができるのかではなく、「あなたが何ができるか」が知りたいのです。
エントリー候補者の中で比較し、”一番優れているから採用!”とはならず、採用人数がゼロのこともあるのです。
そのため、他人と比べてできるかではなく企業の採用基準を満たしているかを意識しましょう。
ハードルを下げて職務経歴書を書く
周りと比較しても何も生まれないので、自分ができることを過不足なく職務経歴書に書くことが重要になります。
自分にとって些細だと感じることでも、自信を持って”経験した”と捉えることが重要です。
なぜならば、企業が求めているレベル(基本的な知識or年単位の経験)が正確には分からない、かつ、条件緩和がされる可能性があるためです。
そのため、自分の知識・経験を過不足なく面接官に伝えることが必要です。
知識・経験・資格はきちんとアピール
知識があるかどうかを応募書類で判断するために、「経験がある」や「資格を持っている」ことは網羅的に書くことを意識しましょう。
少しでも知識があれば、入社後の教育コストを減らすことができるためプラス印象に。
また、”良い意味で”第二新卒は経験が浅いと思われているため、知識があることは想像の何十倍も面接官にとってプラスに映ることがあります。
経験をどのように活かすか
「どのように活かせるか」は「入社後活躍できるか」ということで、自分が経験したことの類似点やプロセスについてを確認します。
ここで重要なのは、今までの成果・結果だけでは「活躍できること」は必ずしもアピールできないということです。
企業側が知りたいことは今までの成果ではなく、入社後に活躍するかの再現性ですよね。
成果や結果ももちろん取り組んだ証明になるため重要ですが、成果だけで転職後も同等の結果を出せることの証明はできません。
つまり大きな成果を求められていると錯覚しがちですが、そうではありません。
自分にとっては小さな結果や成果であっても、取り組みや課題解決のプロセスを証明するために結果を示しアピールしましょう。
ポイント②一番伝えたい経験を伝える
職務経歴書の書き方を調べると、”結論ファースト”や”結論先行型”と検索されます。この”結論”は”自分が最もイイタイコト”を答え・書きます。
つまり、”志望動機”や”強み”など大きなトピックの質問に対しての”最初の答えでイイタイコト”が言えると良いということです。
そうすると面接官は、イイタイコトについての質問しかしてきません。では具体例をみてみましょう。
イイタイコトを伝える具体例
【日常の具体例】
<NG:結論ファーストでない例>
A(男性):「Bさんと一緒にいると楽しいんだよね」
B(女性):「どういうときが楽しいの?」
A:「一緒にでかけた時に、時間忘れて話していて楽しい」
B:「なんで楽しいの?」
A:(いつまでも告白できない。。。)<OK:結論ファーストの例>
A(男性):「付き合ってください!」
B(女性):「なんで付き合いたいの?」
A:「Bさんと一緒にいると楽しいから」
B:「私もAさんとはなしていると楽しい」
このようにイイタイコトを先に言えないと、偶然イイタイコトに関する質問が投げかけられない限り伝えられなくなってしまいます。
日常会話の例で確認しましたが、文章に落とし込んでも全く同じことが言えます。
【”学生時代に最も力を入れたこと”の例】
<NG:結論(イイタイコト)ファーストでない例>
学生時代に力を入れたことは、サッカー部のキャプテンとしての活動です。(面接官の質問の想定:キャプテンとして何をするの?)キャプテンはプレーの指導だけでなく、クラブ全体の運営にも携わりチームのまとめ役です。<OK:結論ファーストの例>
学生時代に力を入れたことは、サッカー部でキャプテンとして各メンバの役割分担をしたことです。(面接官の質問の想定:なんでそれに取り組んだの?)当初、クラブの役割が幹部のみに割り振られており、無職の部員は出席率も悪く部活に対して消極的でした。
前者の例は質問(学生時代に最も力を入れたことは?)に答えられていそうですが、結論部分(第一文)でイイタイコトが伝えられていません。
そのため、最も力を入れたことが結局アピールできずに文章が終わってしまいそうです。
一方後者は、イイタイコトが伝えられているため、分かりやすく質問に答えるだけの論理展開で文章を構成することができます。
イイタイコトは冒頭に
ここまで読むと、会話の中や文章の途中でイイタイコトを書けば・言えばよいのではないかと思った方もいると思います。
しかし、途中にイイタイコトを入れようとすると、論理展開が崩れてしまうことがほとんどです。つまり、質問に答えていないことになりかねません。
そのため、結論としてのイイタイコトをきちんと伝え、質問に答えるようにしましょう。
ポイント③面接官の気になることに答える
もちろん”自分が言いたいことを伝える”ことも大事ですが、大前提として面接官の質問に答える・質問を想定して答えることが必要です。
書類選考や面接は企業側が、採用基準を満たしているか”質問を通じて”判断する場です。
そのため、聞かれていないことには答えず、聞かれたこと”のみ”答えることが求められているのです。
相手軸に職務経歴書を作成すると、質問に振り回されてしまうと思われるかもしれないですが、実はそれで正解です。
経歴書作成に不安な人は転職エージェント登録がおすすめ
みなさんは転職エージェントという言葉を聞いたことがありますか。
このエージェントサービスに登録すると、担当のキャリアアドバイザーから求人紹介だけでなく、面接・選考対策も受けられるのです。
無料で登録ができるので、一切料金はかからずに転職を効率的に進められます。わたしが登録をおすすめする理由はこのようなものが挙げられます。
- 無料で添削サービスが受けられる
- エントリー企業へ推薦をしてくれる
【無料】添削サービスが受けられる
はじめての転職活動では、職務経歴書の書き方が分からないひとも多いハズです。エージェントを利用すると、転職をサポートしてきたプロが選考通過する書類の作成をサポートしてくれます。
また、エントリー企業別に対策してくれるエージェントも多く、企業に採用されやすい書類の書き方も教わることができます。
【選考通過率が上がる】企業への推薦をしてもらえる
添削してもらった後でも、自分の職務経歴書に不安が残る人も多いと思います。
ですが転職エージェントに登録すると、担当のキャリアアドバイザーが企業側へ推薦の連絡を行っています。
そのため、文章だけでは伝わらない魅力を伝えてくれ、書類選考の通過率が一気に挙がるのです。
採用条件の緩和
条件緩和については採用現場で非常によくある考え方です。企業が求める人材に100%マッチした人材が採用できることは非常に少ないです。
採用活動を行っていく中で当初必要としていた条件を緩和して採用をすることもあります。
自分一人では採用条件の緩和や交渉はできないですが、転職エージェントに登録し就職活動をすると、採用されやすくなることが多いのです。
まとめ:他人と比較せずに自分をアピールする
改めてご紹介したポイントをおさらいしましょう。
- ほかの第二新卒と比較しない
- 面接官が気になることにきちんと答える
- 転職が不安な人はエージェント登録がおすすめ
転職しようと考えると「採用されたい」という思いが過剰になり、企業の求める人物像に無意識で合わせ過ぎてしまうことがあります。
そうすると本来の自分がアピールできずミスマッチに繋がってしまう可能性があるだけでなく、もし選考に落ちてしまった場合に納得感が持てなくなってしまいます。
あくまで自分が経験してきたことを過大評価・過小評価せずアピールし、新たな一歩につなげましょう。
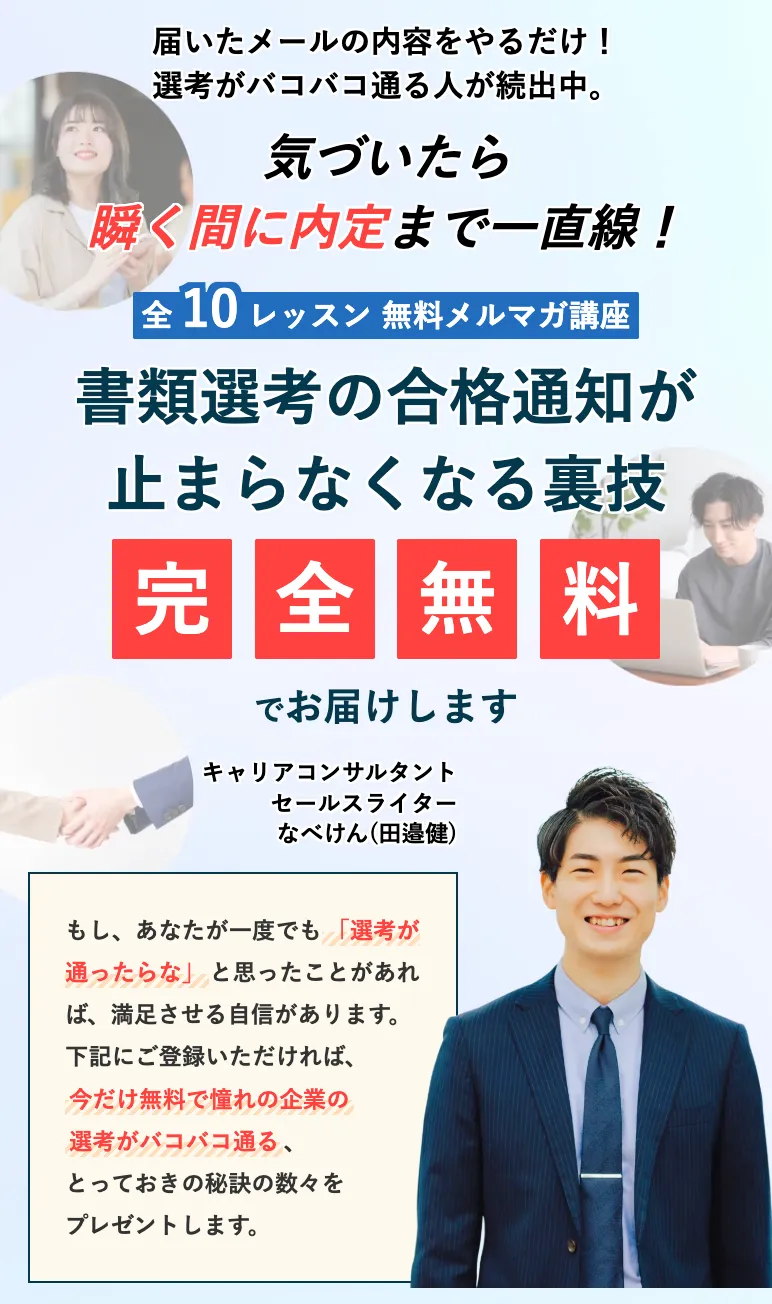

質問や感想をコメント